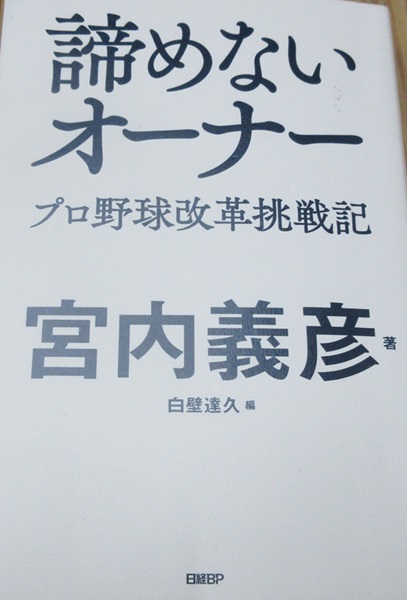
22年限りでオリックス球団のオーナーを退任した宮内義彦氏がそのオーナー人生を回顧した書籍。
88年、社名変更を宣伝する目的で阪急ブレーブスを買収して球界参入。
91年、神戸に移転してチーム名も「ブルーウェーブ」に改称。イチローという不世出のヒーローも出現し、阪神大震災の痛手も「がんばろう神戸」を合言葉に、95・96年と連覇。特に96年は前年なしえなかった「地元胴上げ」「日本一」「打倒巨人」を達成し、ここにストーリーは完結した。
同じ89年からの球界参入組で、(もともとの戦力が違うとはいえ)ずいぶん派手にお金を使うダイエーよりも4年早くリーグ制覇にたどり着いた。ここまでは順調な球団経営と言えよう。
ところが、ここでオーナーは球団の独立採算を強く求めてしまうのだ。
まがりなりにも日本でナンバーワンのプロスポーツ -それも12チームしかない- で採算がとれないのはおかしい、という理屈はわかる。またオリックスグループとして30億程度の赤字は特に問題はないが、かといって日頃事業の採算性を厳しく指導している立場として野球事業だけ慢性的な赤字垂れ流しを容認するという状況もいかがなものか、というのも経営者としてはまっとうな理屈。
ただ、当時はどうしようもなかったんだろう。巨人戦の放映権料(1試合1億と言われる)と付随する観客動員が期待できないパリーグにおいて、努力は収入増を狙うというよりいかに支出を削るか、という方向に向かい
年俸削減→戦力が薄くなる→勝てない→観客減→収入減→戦力流出
の負の無限ループに突入、そして球界再編を迎える。
近鉄との合併はなにより近鉄撤退で空く「大阪」という市場を取りたかった。神戸も阪神に席巻され、大阪も新規参入者に取られたらもはや球団の営業エリアはなくなってしまう。
宮内氏の当時の意向はとにかく球団を12→10(さらには8)まで縮小して、市場のパイの分け前を大きくして何とか採算が取れるようにしたい、というところで、まさか今のように12球団のままパリーグ球団が経営努力で採算がとれるようになったというのは望外だったろう。それでも長くやってれば事態が変わることもあるよね… という話かねえ
たまに好成績の年もあり翌年は優勝すべく補強に力を入れたが、実績のある選手はおおむね高齢(高年俸)でうまく実力を発揮できず、また元の弱いチームに。自前で戦力を育てる方針に転換。
こちらも21-23年の三連覇で結実したように見えたが、24年は調子が上がらずBクラス転落。この先も常勝球団のままかといわれると疑問符は付く。NPBにおいて資金力のあるソフトバンク、巨人、阪神は常勝じゃないとおかしい球団。それ以外は戦力がうまくそろった時期に勝負をかける、といった具合に球界の勢力図は推移していくと自分は考える。
経営者として今更ワシが語るまでもないし、オーナーとしても再編時の読み違えはあったとして、それよりはいい方向に球界が今向かっていると思うので、運もあったのだろう。そして野球好きのオーナーとして最後は「優勝するのを見るまで死んでも死に切れん」みたいな状態になりつつあったので、日本一を見届けて退任というのは最高の花道だったのかなと思う。

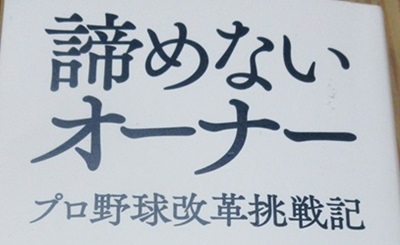


コメント